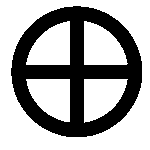年間行事について

法座とは浄土真宗の要となる2部制で執り行う仏徳讃嘆のことをいいます。1部では勤行(お勤め)をし、2部ではご法話(仏さまのお話)を聴聞させていただきます。
手軽さが求められる現代ですが、ご本尊•お荘厳(御仏具、御灯明、御香、仏花等)•お勤め•ご法話、そのすべてが整えられることにより、聞こえ響いてくる世界が仏さまのはたらきです。ぜひお時間を作っていただき、本堂へお参りください。
ここでは正満寺の年間行事についてご紹介します。
※下記の年間行事一覧の法座名を、クリックまたはタップしていただくと法座の説明が表示されます。
お知らせ|News
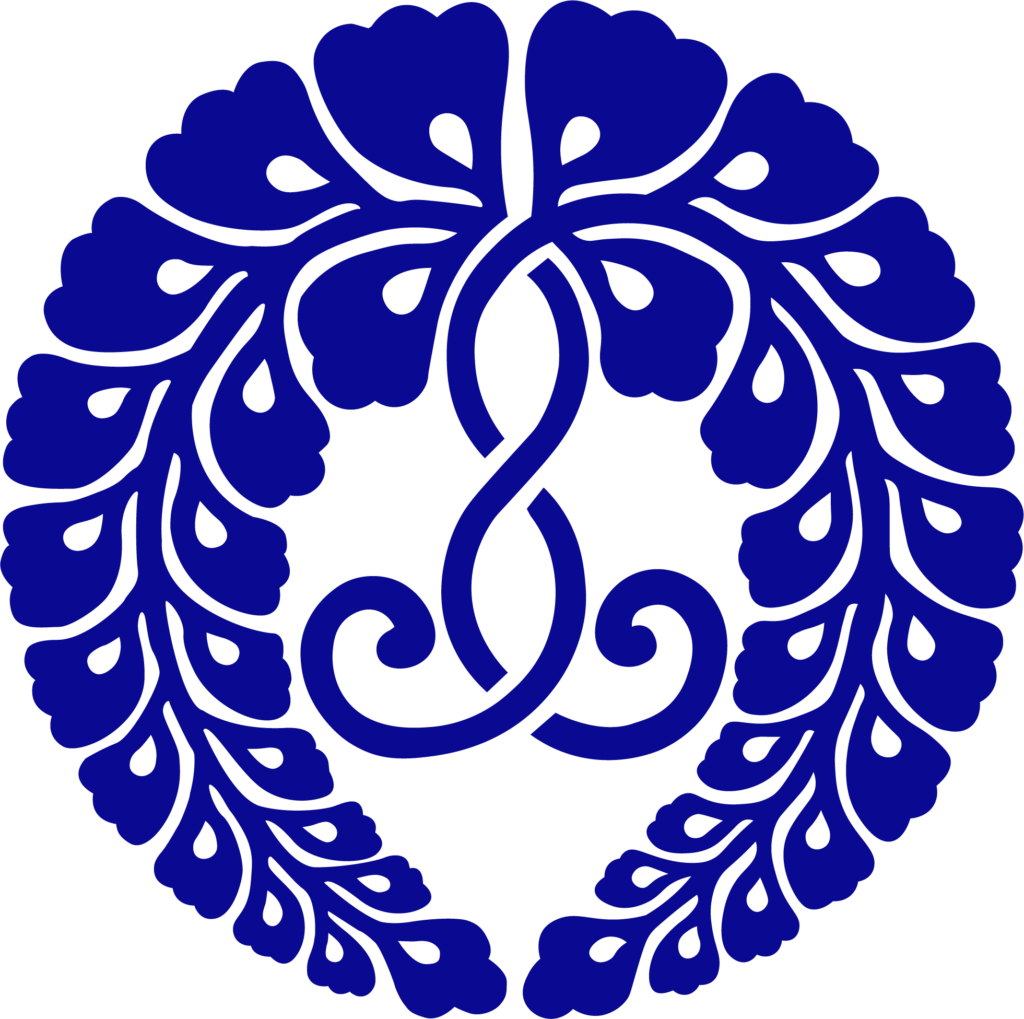
年間法座一覧
親鸞聖人の御祥月命日のこと(旧暦:11月28日、新暦:1月16日)。明治時代に暦は旧暦から新暦に変更されました。その際、旧暦の11月28日は、新暦の1月16日に該当したため、以来、京都の西本願寺(御本山)では、1月16日に合わせて一週間(1月9日~1月16日まで)報恩講が勤められています。1月16日が親鸞聖人の祥月命日ですので、その意味で「御正忌報恩講」とも呼ばれています。親鸞聖人の御祥月命日ですから本来であれば地方の私たちも御本山へお参りすることが望ましいです。しかし、なかなか御本山までお参りにいけないご門徒さんもおられます。地方在住の私たちにとって、一番近いお寺で御祥月命日にも報恩講が勤まれば、京都まで参詣できなくとも安心です。このような理由から地方寺院である正満寺においては旧暦の11月19,20日に報恩講、明けた新暦の1月14,15日に御正忌をそれぞれお勤めさせていただいています。
お彼岸は太陽が真東よりのぼり、真西に沈んでいく年に一度の稀有な2日間です。お浄土(おさとりの世界)は西の方角にあると説かれることから古来より、太陽が真西に沈むお彼岸をお浄土を感じでいく日と大切に御法座を勤めてきました。「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉もあります、季節の変わり目にお浄土のお話をお聴聞してみませんか?
私に繋がる父母等のご先祖のいのち、あるいは私の血となり肉となってくれたであろうすべてのいのち、はてや親鸞聖人やお釈迦さままであらゆるいのちを想い、仏さまのご縁に遇う御法座です。
安居会とも言います。初期仏教の頃のインドではこの時期が雨季に当たり、僧侶が一箇所に集い勉学修行に集中していたそうです。インドの雨季には虫を殺してしまう可能性があるため、外出を避けて修行したことが由来とされています。正満寺では古くから夏法座として勤められてきました。田植えを終えひと段落し泥を落とす意味も含め、いのちと仏さまに向き合ってこられたのでしょうね。
仏教婦人会の皆様主催の御法座です。総会もこの日にあわせて行われます
お釈迦さまのお弟子の一人、目連尊者の母が餓鬼道から救われた際に大いに喜ばれたことに由来します。この時に目連尊者は嬉しくて踊りだし、それが盆踊りのもとだとか…お盆の大型連休で帰省される方も多い時期の御法座です。普段田舎に居られない方にもぜひお参りいただきたいと思います。
お彼岸は太陽が真東よりのぼり、真西に沈んでいく年に一度の稀有な2日間です。お浄土(おさとりの世界)は西の方角にあると説かれることから古来より、太陽が真西に沈むお彼岸をお浄土を感じでいく日と大切に御法座を勤めてきました。「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉もあります、季節の変わり目にお浄土のお話をお聴聞してみませんか?
御法座は男性の参詣が少ない傾向にあります。少しでも多くの男性にお参りいただきたいとの思いから、21世住職惠心が始めた御法座です。あなたのご参詣をお待ちしています。
親鸞聖人の御祥月命日のこと(旧暦:11月28日、新暦:1月16日)。明治時代に暦は旧暦から新暦に変更されました。その際、旧暦の11月28日は、新暦の1月16日に該当したため、以来、京都の西本願寺(御本山)では、1月16日に合わせて一週間(1月9日~1月16日まで)報恩講が勤められています。1月16日が親鸞聖人の祥月命日ですので、その意味で「御正忌報恩講」とも呼ばれています。親鸞聖人の御祥月命日ですから本来であれば地方の私たちも御本山へお参りすることが望ましいです。しかし、なかなか御本山までお参りにいけないご門徒さんもおられます。地方在住の私たちにとって、一番近いお寺で御祥月命日にも報恩講が勤まれば、京都まで参詣できなくとも安心です。このような理由から地方寺院である正満寺においては旧暦の11月19,20日に報恩講、明けた新暦の1月14,15日に御正忌をそれぞれお勤めさせていただいています。
12月31日23時30分頃~除夜の鐘をつき始め、本堂内で勤行を行います。引き続き1月1日0時過ぎより新年の勤行(修正会)を行います。