正満寺について

ぶろぐ|Blog
- 鐘つき鐘つき 前坊守が下手べたと鐘をつき始めて早いもので13年になります。その前 …
- ホームページ開設しました‼ホームページ開設しました‼ 弟の全面協力により、ついにホームページが完成し …
正満寺について
Shoumanji’s History
室町時代後期の天文11年(1542)、薩摩国白沢津(現在の鹿児島県枕崎市白沢西町)出身の
島津薩摩守頼忠が
甲山城主上原元祐を頼り、出家して
康雲と名乗り、天台宗の寺院として正満寺を開基しました。
慶長13年(1608)、
3世念尊は
本願寺12代准如御門主より木仏免許下附賜り、浄土真宗本願寺派の寺院となりました。
その後、江戸時代中期以降は学僧を多数輩出しています。
天明8年(1788)〜寛政3年(1791)までは
大瀛が住職を勤めています。
嘉永4年(1851)には
12世惠海が
本願寺派勧学(本願寺派の学階)を拝命し、「学心館」という寮を開きました。
門弟には護命、義海、福間浄観、足利義山らが学びました。
その間、度重なる火災による建屋の焼失、飢饉や一揆、住職後継問題など様々な困難に直面しました。
しかし、それぞれの時代の地域や門信徒の皆様お力添えに支えていただき、いまに至ります。
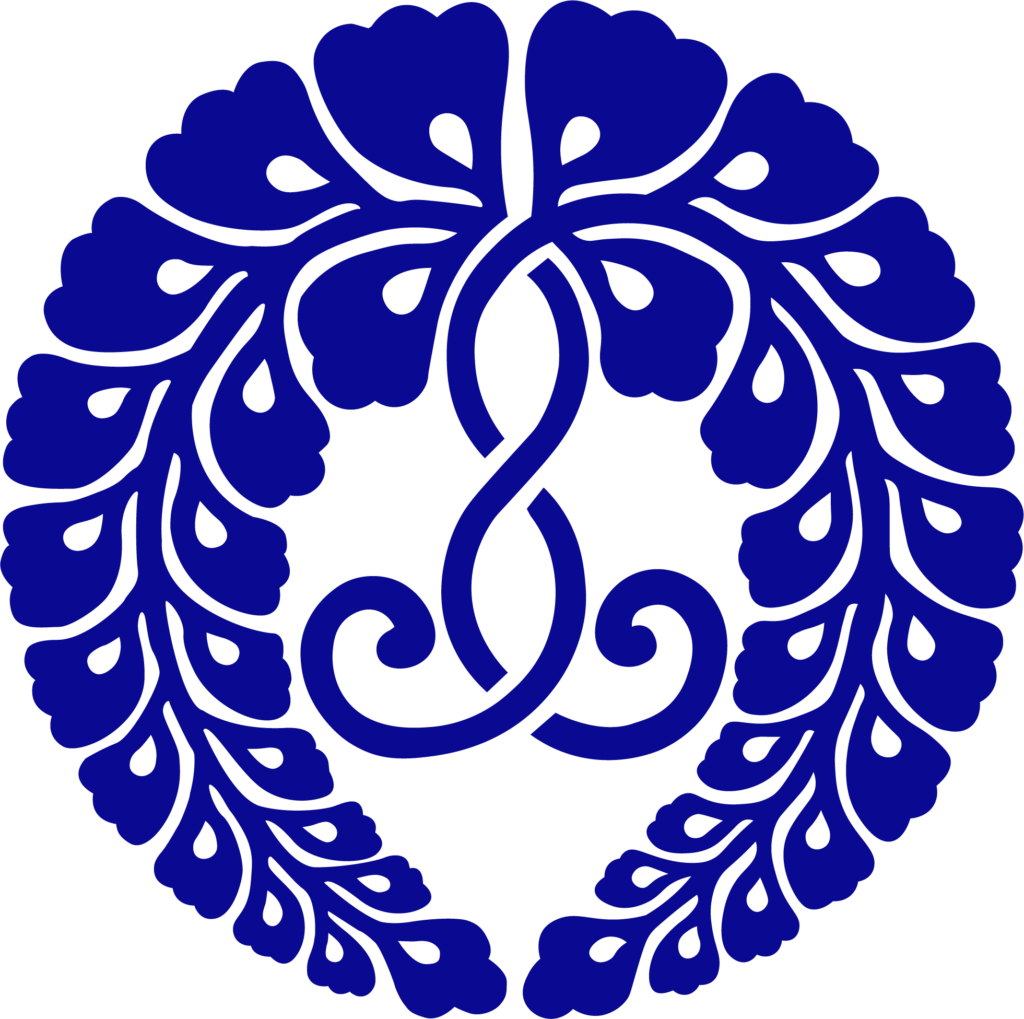
about the Shin-Buddhism
浄土真宗
仏教は西暦五〇〇年代半ばに百済から伝えられました。
五〇〇年代後半には聖徳太子のご活躍によって、日本に定着していきました。
その後平安末期から鎌倉初期にかけ、これまで「難解で」「貴族だけのもの」であった仏教を、新しく解釈していく大きな動きが起こりました。
それまでの仏教は私たちが俗世を離れ、難行苦行や勉学に励み、また厳しい戒律を守って仏に近づいていくものでした。
宗祖親鸞聖人は釈尊が語られたたくさんのお説教の中から、三つ(『仏説無量寿経』『仏説観無量寿経』『仏説阿弥陀経』)に注目され、特に大切なものと仰がれました。
中でも最も大切な『仏説無量寿経』に説かれているのは「自ら仏になることのできない、あなたを必ず仏にしたい」との阿弥陀如来の大きな願いです。
この阿弥陀如来の「ご本願」を拠り所とし、南無阿弥陀仏とお念仏申すみ教えを「浄土真宗」といいます。
ギャラリー|Gallery





正満寺:本堂と境内の様子
世羅の大自然を背に、どっしりとお堂を構える正満寺では、四季折々の空気や景色を堪能することが出来ます。本堂では年に10回のご法座や、月に1回、仏教婦人会の方々がコーラスを開催してくださったり、門信徒の方々が一丸となってお寺を支えてくださっています。ご法座の詳細は下のボタンからご確認ください。


