
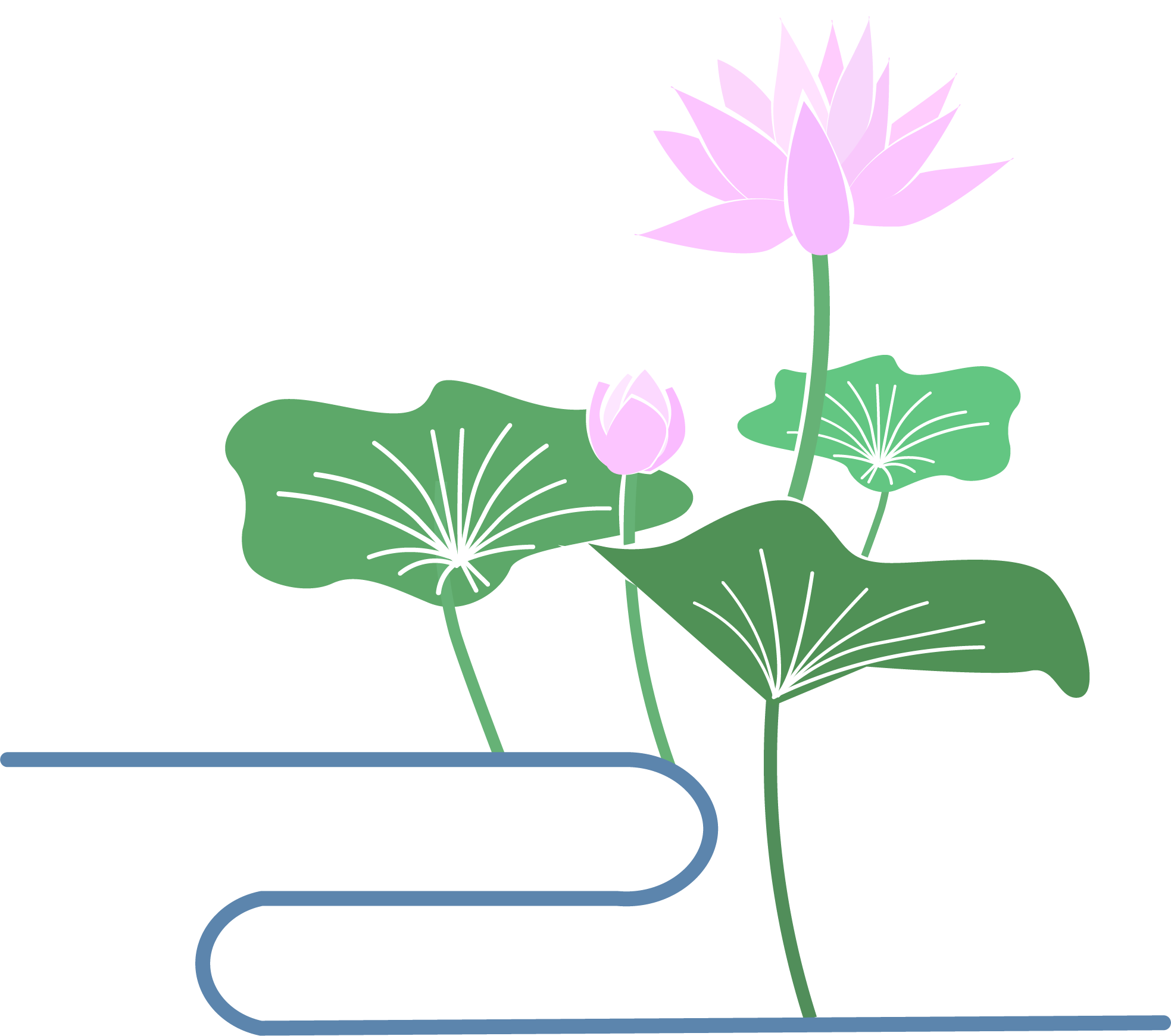
地域と門信徒の皆様に支えられ、
受け継がれ、まもなく五〇〇年
受け継がれ、まもなく五〇〇年
新着情報| News
- 鐘つき鐘つき 前坊守が下手べたと鐘をつき始めて早いもので13年になります。その前は亡き前々坊守の義母が70年もの長き …
- ホームページ開設しました‼ホームページ開設しました‼ 弟の全面協力により、ついにホームページが完成しました。マメな性格ではないのでブログ …

正満寺について
History
室町時代後期の天文11年(1542)、薩摩国白沢津(現在の鹿児島県枕崎市白沢西町)出身の
島津薩摩守頼忠が
甲山城主上原元祐を頼り、出家して
康雲と名乗り、天台宗の寺院として正満寺を開基しました。
慶長13年(1608)、
3世念尊は
本願寺12代准如御門主より木仏免許下附賜り、浄土真宗本願寺派の寺院となりました。
その後、江戸時代中期以降は学僧を多数輩出しています。
天明8年(1788)〜寛政3年(1791)までは3年間
大瀛が住職を勤めています。
嘉永4年(1851)には
12世惠海が
本願寺派勧学(本願寺派の学階)を拝命し、「学心館」という寮を開きました。
…


阿弥陀如来立像について
The Amitabha Buddha
Statue,
an Important Cultural
Property
天文11年(1542)甲山城主上原元祐寄進との記録があります。
伝承には源信作と伝わっています。
専門家の鑑定を受けましたら、制作は平安時代後期と推定されており、年代としては源信和尚の頃で間違いないようです。
令和の大修復以前は本堂内陣右余間にご安置してありましたが、現在は大田庄歴史館に仮安置していただいております。
門信徒会館完成後には、1階仏間にご安置させていただく予定です。
正満寺護寺会
仏教婦人会について
仏教婦人会について
About a member of the Shoumanji
正満寺護寺会は昭和37年(1962)17世惠見が逝去したのを機に、数名の門信徒の呼びかけがあり多くの門信徒の皆様の賛同を得て護持を目的に「恵会」と名を冠し発足されました。
平成に入り「恵会」という名称は「正満寺護持会」に改められ、今日に至ります。活動内容は裏山の草刈り作業や行事•会計報告など多岐に渡ります。
仏教婦人会は正満寺諸行事全般にご協力いただいています。各法座における御斎(昼食)のレシピ考案•調理•片付け、聞法のつどい(仏教婦人会法座)、年1回の研修旅行、月1回のコーラスなど、すべて婦人会のみなさんが主体となって実働くださっています。
…

年間行事について
Shin Buddhist Dharma
talk
正満寺では年に10回の法座活動を行っています。法座とは浄土真宗の要となる2部制で執り行う仏徳讃嘆のことをいいます。1部では勤行(お勤め)をし、2部ではご法話(仏さまのお話)を聴聞させていただきます。
手軽さが求められる現代ですが、ご本尊•お荘厳(御仏具、御灯明、御香、仏花等)•お勤め•ご法話、そのすべてが整えられることにより、聞こえ響いてくる世界が仏さまのはたらきです。ぜひお時間を作っていただき、本堂へお参りください。
仏事に関するご相談
Contact
正満寺では年間行事以外にも本堂で葬儀や法事などの仏事を行えます。葬儀・法事・合同墓をご検討の方。その他、仏事に関して分からないことなどお気軽にお問い合わせください。
葬儀のご連絡に関しては受付時間外も対応いたします。
詳しくはこちらのボタンからご確認ください。

アクセス|Access
住所
〒722-1123
広島県世羅郡世羅町甲山無番地
広島県世羅郡世羅町甲山無番地
交通アクセス
(1)甲山営業所より徒歩5分
(2)備後三川駅より車で13分
(2)備後三川駅より車で13分
駐車場
あり / 20台 無料


